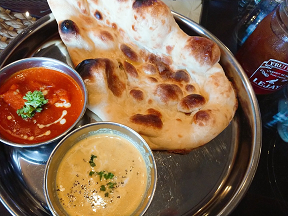修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(104)
今回は修士論文の第2章第2節第5項第2号の第3回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回は、支払損害賠償金の経費性を検討しています。
「ただし、重過失の有無の判定は微妙で、判定困難な場合が少なくない。この点について国税庁通達は、その者の職業、地位、加害当時の周囲の状況、侵害した権利の内容及び取締法規の有無等の具体的な事情を考慮して、その者が払うべきであった注意義務の程度を判定し、不注意の程度が著しいかどうかにより判定するものとし、一定の場合1には、特別な事情がない限り、その行為者に重大な過失があったものと判定するものとしている。」
1 一定の場合とは次のような場合をいう。
「自動車等の運転者が無免許運転、酔払運転、信号無視その他道路交通法第4章第1節《運転者の義務》に定める義務に著しく違反すること又は雇用者が超過積載の指示、整備不良車両の運転の指示その他同章第3節《使用者の義務》に定める義務に著しく違反することにより他人の権利を侵害した場合」「劇薬又は爆発物等を他の薬品又は物品と誤認して販売したことにより他人の権利を侵害した場合」(所得税基本通達45−8(一)、(二))
先週の土曜日に家族3人で、茨城県坂東市にあるミュージアムパーク茨城県自然博物館へ行ってきました。息子が、「ティラノサウルスとトリケラトプスがケンカしてるの行きたい」というので、これで訪問するのは3、4回目になります。この博物館は息子も気に入っているようです。ただ、博物館のショップに行くと必ず何か買いたがるので、困ってしまいます。
(2022年9月6日)